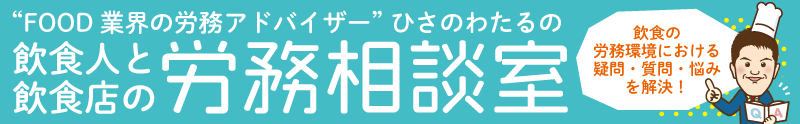
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「アルバイトにはアルバイト用就業規則だけ見せればよいのか」

Q.
アルバイトとして飲食店で働いています。私のお店には、就業規則があるのですが、アルバイトはアルバイト用の就業規則だけ見ることができて、正社員用のは見せてもらえません。なんだか隠し事をされているような気がするのですが…。
【24才 女性】
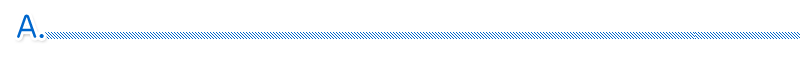
A.
労働基準法の定めにより、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければいけません(89条)。また、作成にあたっては、労働者の過半数代表者の意見を聴かなければなりません(90条)。そして、届け出た就業規則は、労働者に周知させなければなりません(106条)。また、労働契約法では、就業規則の内容が合理的で、かつ労働者に周知させていた場合には、その就業規則は労働契約の内容になる、としています(7条)。この「周知」とは、「労働者が見ようと思えば、いつでも見られる状態」であることをいいます。いくら労働基準監督署に届出済みの就業規則でも、社長の金庫の中にしまい込んでいては、「周知」したことにはならず、その就業規則は法的効力を持ちません。それだけ、就業規則を労働者に周知させるというのは、重要なことなのです。
さて、正社員とアルバイトでは、さまざまな点で労働条件に違いがあるものです。そのため、就業規則は正社員用、アルバイト用といった具合に、雇用形態別に分けて作成することが一般的となっています。ただし、行政解釈によると、「別個の就業規則を定めた場合には、当該二以上の就業規則を合したものが法第89条の就業規則になるのであって、それぞれ単独に同条に規定する就業規則となるものではない」とされています。つまり、正社員用、アルバイト用と分けて作成しても、それらが一体となって一つの「就業規則」となるのです。
そのため、先述の意見聴取義務についても、正社員用は正社員の代表者から、アルバイト用はアルバイトの代表者から、意見を聴く必要はありません。あくまでも、そのお店の正社員、アルバイト等含めたスタッフ全体の代表者から意見を聴くことが、労働基準法上の義務となっています(なお、それとは別に、パートタイム労働法では、アルバイト用はアルバイトの代表者から意見を聴くように努めなければならないとされています)。
そして、周知義務についても、例外とする定めはありません。したがって、正社員用、アルバイト用を合わせたものを一つの就業規則として、事業場で周知させなければならないと考えるべきでしょう。
さて、正社員とアルバイトでは、さまざまな点で労働条件に違いがあるものです。そのため、就業規則は正社員用、アルバイト用といった具合に、雇用形態別に分けて作成することが一般的となっています。ただし、行政解釈によると、「別個の就業規則を定めた場合には、当該二以上の就業規則を合したものが法第89条の就業規則になるのであって、それぞれ単独に同条に規定する就業規則となるものではない」とされています。つまり、正社員用、アルバイト用と分けて作成しても、それらが一体となって一つの「就業規則」となるのです。
そのため、先述の意見聴取義務についても、正社員用は正社員の代表者から、アルバイト用はアルバイトの代表者から、意見を聴く必要はありません。あくまでも、そのお店の正社員、アルバイト等含めたスタッフ全体の代表者から意見を聴くことが、労働基準法上の義務となっています(なお、それとは別に、パートタイム労働法では、アルバイト用はアルバイトの代表者から意見を聴くように努めなければならないとされています)。
そして、周知義務についても、例外とする定めはありません。したがって、正社員用、アルバイト用を合わせたものを一つの就業規則として、事業場で周知させなければならないと考えるべきでしょう。
グルメキャリー201号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

