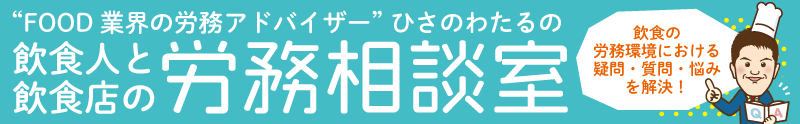
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「入れ墨を入れたことを理由に解雇は認められるか」

Q.
飲食店でホール係をしています。先日、ファッションで、二の腕に入れ墨を入れました。すると、店長から「接客業で入れ墨をするとは何ごとだ! 解雇だ!」と言われました。お店の制服は一年中長袖でお客様からは見えないし、入社の時から入れ墨禁止とされていたわけでもないのに、解雇は認められるのですか。
【23才 男性】
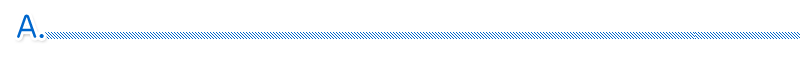
A.
結論としては、お店側が解雇をするのは難しいでしょう。
まず、容姿、服装、髪型等、「どんな格好」をするかは、個人の趣味や嗜好に属することであり、本来は各人の自由です。これが大原則です。とはいえ、いくら私生活上の自由があるとはいえ、労働契約を締結して職場で働くということは、その職場の秩序を維持することが求められます。そのために、使用者(お店の側)は、身だしなみについても、経営上の必要な範囲で合理的な規制を定めることは認められています。そして、この合理性の基準は、職種や職務内容によって判断されます。
たとえば、口ひげを生やしていたハイヤー運転手に関する裁判例では、「人の心情に依存する要素が重要な意味を持つサービス提供を本旨とする業務においては、身だしなみ、言行などが企業の信用、品格保持に深甚な関係を有するから、他の業種に比して一層の規制が課せられるのはやむを得ない」と規制を課すこと自体は認めました。しかし、「規制の対象となるのは、無精ひげとか異様・奇異なひげだけである」として、本件では口ひげを剃る必要はない、と判断しました。
また、トラック運転手が茶髪を理由に解雇された事案では、「髪の色や形、容姿、服装といった人の人格や自由に関する事項を制限する場合、企業の円滑な運営に必要かつ合理的な範囲にとどまるべき」として、裁判所は解雇を無効と判断しました。
ただ、入れ墨は、ひげや茶髪と比べ、社会に受け入れられているわけではなく、同じ基準で論じることはできないでしょう。ましてや、接客業や社外の取引先と接する業務の場合には、相手に恐怖感や不快感を与えたり、反社会的勢力とのつながりを疑われたりするものです。したがって、入れ墨を禁止する規制は、通常の身だしなみ規制より広く認められるでしょう。ただし、その規制も、「顧客から見える部位に入れ墨がある場合に限る」と、限定的な解釈になると考えられます。
ご質問のケースは、一年を通してお客様からは見えない部位に入れ墨があること、お店には入れ墨を禁止する規制がなかったこと、からすると、解雇は無効となる可能性が高いでしょう。
まず、容姿、服装、髪型等、「どんな格好」をするかは、個人の趣味や嗜好に属することであり、本来は各人の自由です。これが大原則です。とはいえ、いくら私生活上の自由があるとはいえ、労働契約を締結して職場で働くということは、その職場の秩序を維持することが求められます。そのために、使用者(お店の側)は、身だしなみについても、経営上の必要な範囲で合理的な規制を定めることは認められています。そして、この合理性の基準は、職種や職務内容によって判断されます。
たとえば、口ひげを生やしていたハイヤー運転手に関する裁判例では、「人の心情に依存する要素が重要な意味を持つサービス提供を本旨とする業務においては、身だしなみ、言行などが企業の信用、品格保持に深甚な関係を有するから、他の業種に比して一層の規制が課せられるのはやむを得ない」と規制を課すこと自体は認めました。しかし、「規制の対象となるのは、無精ひげとか異様・奇異なひげだけである」として、本件では口ひげを剃る必要はない、と判断しました。
また、トラック運転手が茶髪を理由に解雇された事案では、「髪の色や形、容姿、服装といった人の人格や自由に関する事項を制限する場合、企業の円滑な運営に必要かつ合理的な範囲にとどまるべき」として、裁判所は解雇を無効と判断しました。
ただ、入れ墨は、ひげや茶髪と比べ、社会に受け入れられているわけではなく、同じ基準で論じることはできないでしょう。ましてや、接客業や社外の取引先と接する業務の場合には、相手に恐怖感や不快感を与えたり、反社会的勢力とのつながりを疑われたりするものです。したがって、入れ墨を禁止する規制は、通常の身だしなみ規制より広く認められるでしょう。ただし、その規制も、「顧客から見える部位に入れ墨がある場合に限る」と、限定的な解釈になると考えられます。
ご質問のケースは、一年を通してお客様からは見えない部位に入れ墨があること、お店には入れ墨を禁止する規制がなかったこと、からすると、解雇は無効となる可能性が高いでしょう。
グルメキャリー246号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

