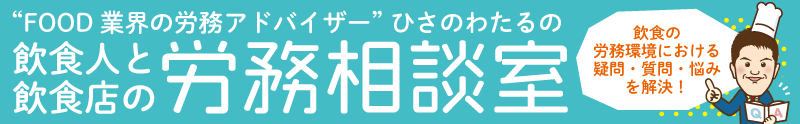
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「求人広告に記載が無く、入社時説明もなかったが、就業規則にあった試用期間は有効か」

Q.
入社して3ヶ月たったところで、「職務不適格により、試用期間満了をもって本採用しない」と通告され、解雇されました。しかし、試用期間については、求人広告に記載がなかったし、入社時にも説明がありませんでした。先ほどの通告を受けて、就業規則に記載されていることを初めて知りました。こんな試用期間制度が認められるのでしょうか。
【31才 女性】
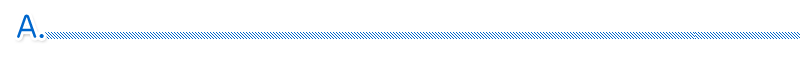
A.
本採用拒否が有効と認められるかどうかは別問題として、試用期間の制度については、有効と判断される可能性があります。以下、ポイントを一つずつ解説します。
まず、試用期間とは、従業員としての適格性や能力の有無を判断するための観察期間のことであり、多くの企業で設けられています。試用期間の長さについて規制はありませんが、一般的には3~6ヶ月であることが多いです。法的には、試用期間は「解約権留保付労働契約」が成立していることになります。本採用を拒否するということは、この解約権を行使することであり、解雇の一種となります。ただし、通常の解雇よりは、使用者(お店の側)に、広い範囲の裁量が認められています。なお、本採用拒否も解雇である以上、労働基準法20条により、30日前以上に解雇予告または平均賃金30日分以上の解雇予告手当が必要です(試用期間開始14日以内の解雇を除く)。
次に、求人広告についてです。労働者の募集を行う際、ハローワークに求人を出したり、雑誌等に求人広告を掲載するにあたって、賃金、労働時間等、一定の労働条件を明示しなければなりません(職業安定法5条の3、42条)。しかし、この一定の労働条件には、「試用期間の有無」は含まれていません(ただし、実際のハローワークの求人票には、試用期間について記載欄があります)。したがって、求人広告に試用期間の記載がなかったことは、法的には問題ないことになります。また、求人広告は労働契約の申込の誘因であり、求人広告と異なる労働条件で合意が成立した場合、そちらの労働条件が労働契約の内容となります。
その次は、入社時の説明についてです。入社後の労働条件について、「言った、言わない」のトラブルが起きることがあります。これを防止するために、労働契約の締結に際し、重要な労働条件について明示することが義務づけられていて、特に重要な事項については書面を交付しなければなりません(労働基準法15条)。実は、こちらの明示事項にも、試用期間については含まれていません(ただし、学説の中には、試用期間についても明示が必要との見解もあります)。したがって、入社時に試用期間の明示がなかったことについても、直接法律違反になるわけではありません。もっとも、労働契約法4条1項には、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」と、訓示的に定められています。採用時に試用期間について十分な説明をしなかったことが、本条違反となる可能性はあるでしょう。
最後に、就業規則には記載があった点です。入社時に、合理的な内容の労働条件が定められている就業規則を、労働者に周知させていた場合、この就業規則は法的効力を持ち、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件となります(労働契約法7条)。ここでいう「周知」とは、労働者が見ようと思えばいつでも見られる状態のことであり、実際に見たかどうかは問題となりません。したがって、試用期間について、合理的な内容で規定されている就業規則が、いつでも見られる状態になっていた場合、仮にあなたが見ていなかったとしても、この試用期間は労働契約の内容となっていたことになります。
以上のとおり、試用期間について、求人広告に記載が無く、入社時の説明も無くても、法的に有効な就業規則に記載されていた場合、その試用期間の制度は有効と認められる可能性が考えられます。
まず、試用期間とは、従業員としての適格性や能力の有無を判断するための観察期間のことであり、多くの企業で設けられています。試用期間の長さについて規制はありませんが、一般的には3~6ヶ月であることが多いです。法的には、試用期間は「解約権留保付労働契約」が成立していることになります。本採用を拒否するということは、この解約権を行使することであり、解雇の一種となります。ただし、通常の解雇よりは、使用者(お店の側)に、広い範囲の裁量が認められています。なお、本採用拒否も解雇である以上、労働基準法20条により、30日前以上に解雇予告または平均賃金30日分以上の解雇予告手当が必要です(試用期間開始14日以内の解雇を除く)。
次に、求人広告についてです。労働者の募集を行う際、ハローワークに求人を出したり、雑誌等に求人広告を掲載するにあたって、賃金、労働時間等、一定の労働条件を明示しなければなりません(職業安定法5条の3、42条)。しかし、この一定の労働条件には、「試用期間の有無」は含まれていません(ただし、実際のハローワークの求人票には、試用期間について記載欄があります)。したがって、求人広告に試用期間の記載がなかったことは、法的には問題ないことになります。また、求人広告は労働契約の申込の誘因であり、求人広告と異なる労働条件で合意が成立した場合、そちらの労働条件が労働契約の内容となります。
その次は、入社時の説明についてです。入社後の労働条件について、「言った、言わない」のトラブルが起きることがあります。これを防止するために、労働契約の締結に際し、重要な労働条件について明示することが義務づけられていて、特に重要な事項については書面を交付しなければなりません(労働基準法15条)。実は、こちらの明示事項にも、試用期間については含まれていません(ただし、学説の中には、試用期間についても明示が必要との見解もあります)。したがって、入社時に試用期間の明示がなかったことについても、直接法律違反になるわけではありません。もっとも、労働契約法4条1項には、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」と、訓示的に定められています。採用時に試用期間について十分な説明をしなかったことが、本条違反となる可能性はあるでしょう。
最後に、就業規則には記載があった点です。入社時に、合理的な内容の労働条件が定められている就業規則を、労働者に周知させていた場合、この就業規則は法的効力を持ち、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件となります(労働契約法7条)。ここでいう「周知」とは、労働者が見ようと思えばいつでも見られる状態のことであり、実際に見たかどうかは問題となりません。したがって、試用期間について、合理的な内容で規定されている就業規則が、いつでも見られる状態になっていた場合、仮にあなたが見ていなかったとしても、この試用期間は労働契約の内容となっていたことになります。
以上のとおり、試用期間について、求人広告に記載が無く、入社時の説明も無くても、法的に有効な就業規則に記載されていた場合、その試用期間の制度は有効と認められる可能性が考えられます。
グルメキャリー267号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

